2025.07.16
社会科教育(橋本ゼミ)では、6月25日(水)の4限に、本学ラーニングラボの教職特命教授であり、元日本人学校校長でもある川口浩先生をお迎えして、「世界から見た日本の教育」をテーマにご講義いただきました。
6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、 12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている
これは映画「小学校~それは小さな社会~」の中の一言です。私たちは小学校で日本人になります。日本に住んでいる私たちはそれを常識として疑うことはあまりありません。しかし、今回の講義で世界を鏡として日本の教育を考えたときに、私たちの常識が必ずしも世界のスタンダードではないことに気が付きました。私たちは、今回の講義日本の教育が他国では必ずしも当たり前ではないことを再認識し、自分たちが受けてきた日本型教育について考えを深める貴重な機会となりました。

【学生の感想】
今回の特別講義を通して、日本の教育の在り方について深く考えさせられた。特に「日本人は小学校でつくられる」という言葉は印象的であり、日本の学校教育が個性よりも集団性を重視し、社会に適応する力を育むことを目的としているという指摘には納得がいった。 一方、外国では「自分の意見を持つ」「主張する」ことが重要視される傾向にあるという比較から、日本の教育が持つ特色と限界が浮き彫りになった。講義後半の活動では、日本人の協 調性や礼儀正しさが評価されるが、それは同時に「個性の抑制」の裏返しであるとも感じた。今回の講義は、日本の教育を見直すきっかけとなり、今後教員を目指す上で「集団」と「個人」のバランスについて再考する必要性を強く感じた。
小学校6年間の学びの中で日本人が作られていくと学び、これから教師になるにあたってすごく責任重大なことをする立場になるのだと改めて感じました。教師という仕事は本当に毎日忙しいと思いますが、目の前の事にただ精一杯になって1日が終わってしまうのではなく、普段の子供達との関わりの中で少しでも子供の良さや個性を伸ばしていける教師になりたいと強く思いました。また礼儀や優しさ、責任などが大切であるという教えの中でも、自分自身はどうしたいのかという意見を持つことの大切さや、自分自身の良さを大切にしてほしい事も伝えられる教師になりたいと感じました。とても面白く、これからの私にとって必要なことを考えられた講義でした。ありがとうございました。映画の「それは小さな社会」絶対に教師になる前に見に行きます!
改めて学校教育はどうあるべきなのかということを考えることができました。日本はみんなと同じでなければいけないことを表した図とアメリカの個性を出さなければいけない図が印象的でした。どちらにもよさはあるけれど、どちらにも課題もあり、そのどちらとものよさを生かした教育ができたらもっとよくなるだろうと思いました。日本型教育の「個を大切にする」という課題を少しでもよくするために私自身が教壇に立った時に一人一人をしっかり見て、子どもたち全員のそれぞれのよさを伸ばしてあげられる教員になりたいと思いました。それと同時に教員それぞれが「一人一人をよく見て個を大切にしよう、日本の教育をよくしよう」とするのには限界があるのではないかと考えました。国としてもよりよく日本の子どもを育てるために、よい教育を提供するためにどうするべきか考えていかないといけないとも思いました。その一方で、日本の教育を他国が真似するくらいよい面もあるということを知れました。どうしても悪いところに目が行きがちですが、日本の教育にも強みがあるということが改めて分かり誇らしく感じました。「日本人は小学校でつくられる」この言葉を胸に教壇に立ちたいと思います。様々なことを考えるきっかけになりました。
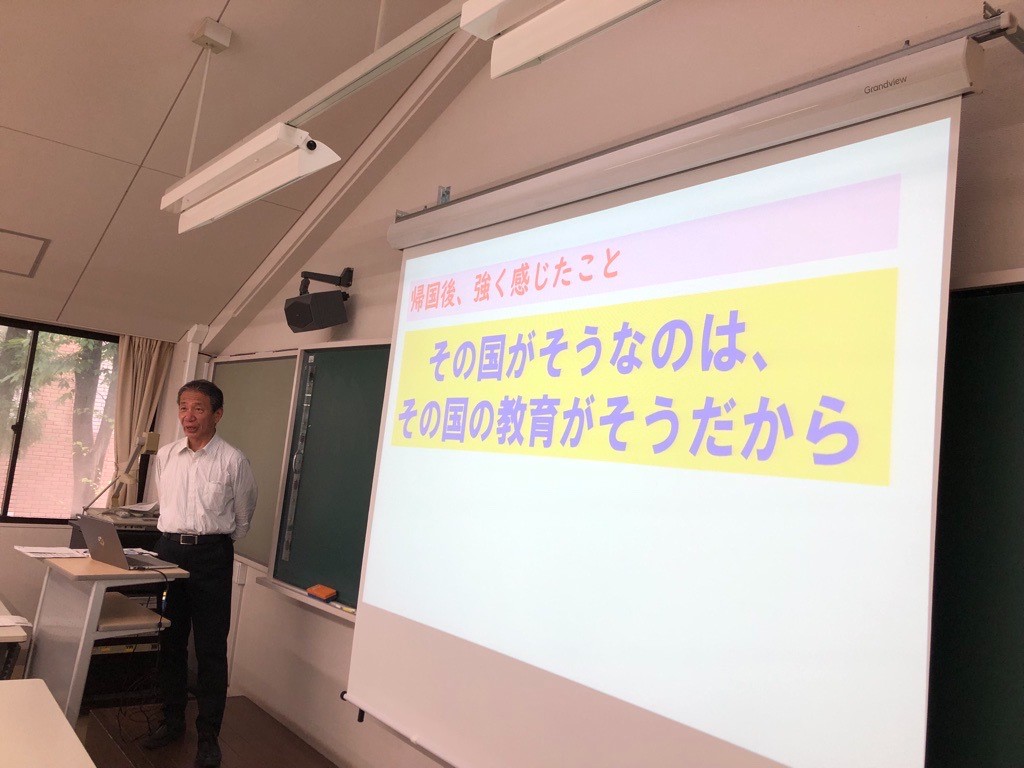
日本で当たり前のように行われている教育活動が海外からはとても変わっていると思われていること、また、日本の教育活動を取り入れようとしていること、そして、海外が日本の教育の特色を取り入れた際の懸念など、普段ではあまり気づかない視点に気づけたと思います。「個人の尊重」という観点では日本の教育ではまだまだできることもあると思いますので、今後教育に携わっていく人間として、今回の学びを生かしていきたいと思いました。
今回の特別講義を通して、日本の教育の在り方について深く考えるきっかけをいただきました。特に「日本人は小学校でつくられる」という言葉は非常に印象的であり、これから教師を目指す立場として、改めて自分が担う責任の重さを痛感しました。 日本の学校教育は、個性よりも集団性を重視し、社会に適応する力を育むことを目的としているという指摘には大きく頷かされました。一方で、外国の教育では「自分の意見を持つこと」「主張すること」が重要視されているという比較から、日本の教育が持つ特色と限界の両面が浮き彫りになったように感じました。 教師という職業は、日々多忙で目の前のことに追われがちかもしれませんが、その中でも、子どもたち一人ひとりの良さや個性を見つけ、少しでも伸ばしていけるような関わり方をしていきたいと強く思いました。また、協調性や礼儀、責任といった社会性を育むと同時に、自分はどうしたいのかなどといった内面の意見や、自分らしさを大切にできる子どもたちを育てられる教師でありたいと感じました。
今回の講義を聞いて、日本の学校教育がどうあるべきか深く考えられました。小学校生活の学びの中で日本人は作られるという言葉を聞いて教師を目指す上で教育が個人の人格形成に与える影響の大きさを痛感しました。そのため、教員達は毎日、児童の宿題や保護者対応など目の前の課題で精一杯ではあるが、児童達と触れあっていき、少しずつ児童の自己肯定感や個性を伸ばしていくことが重要だということが分かりました。また、日本の教育は集団性や協調性を重視する一方で、個性の尊重や自己主張を育むという点では課題が残りますが、礼儀正しさや責任感といった美徳を育む日本の教育は、世界からも評価されるべき強みであることを知ることができ、海外にはない日本独自の教育があって、嬉しいです!今回の講義を通して、民間企業で多様な価値観を理解し、尊重する姿勢を大事にしていき、お客様と接していきたいと思います。
講義のなかで日本型教育の良さと課題がとても印象に残りました。特別活動や道徳は日本の礼儀正しさや責任感の強さにとても大きな影響を与えていて、外国の教育にも取り入れたいと思えるほどいいものであるということが改めてわかりました。一方でそういった感覚が同調圧力になり、連帯責任に繋がり日本にいたら、飛び抜けることも許されないといった感覚になってしまうということにも改めて気づきました。集団としてだけでなく、一人ひとりの個も大切にできるように、どうすればよりよい教育ができるのか今後も考えていきたいです。
日本の教育がどれだけ人格形成に大きな影響を与えているかを改めて考えるきっかけになりました。集団の安定を重視している日本と、個を大切にしているアメリカの価値観の対比は特に印象的でした。どちらにも良さと課題があると知りました。そのため、「個を大切にする」教育も日本に取り入れていくことで、よりよい教育になると思いました。「しっかり見ていれば個で対応できる部分は沢山ある」という言葉を聞いて、今後、教員になった時は、子どもたち一人一人への日々の声かけや、関わりを大切にしたいと思いました。
今回の講義より日本の教育と世界の教育は大きく異なり、良いところも悪いところもあるのが現状だと分かりました。また、小学校教員は子どもたちの人格形成に大きく影響与える立場であり、とても重い責任を担っていることがよく分かりました。私は子どもたち一人一人の個性も尊重することで、子どもたちも他者を尊重できるようになっていくのではないかと考えました。今後も世界と日本の教育の違いについて関心を持ち、まだ知らない文化から広い視点を得られるようになりたいと思います。
日本の教育が人格形成に与える影響について深く考える機会となりました。特に、日本が集団の安定を重視し、アメリカは個を尊重するという価値観の対比が印象に残りました。どちらにも良さと課題があると感じ、日本でも「個を大切にする教育」を取り入れることで、より良い教育が実現できると考えました。「しっかり見ていれば個で対応できる部分は沢山ある」という言葉が心に残り、教員として子ども一人ひとりに寄り添った声かけや関わりを大切にしたいと思いました。また、日本型教育の強みである特別活動や道徳は、礼儀や責任感を育む面で優れた要素であると再認識しましたが、一方で同調圧力や連帯責任といった課題も感じました。今後も、個と集団のバランスを意識し、よりよい教育の在り方を考えていきたいです。
日本の教育がどれだけ人格形成に大きな影響を与えているかを改めて考えるきっかけになりました。集団の安定を重視している日本と、個を大切にしているアメリカの価値観の対比は特に印象的でした。どちらにも良さと課題があると知りました。そのため、「個を大切にする」教育も日本に取り入れていくことで、よりよい教育になると思いました。「しっかり見ていれば個で対応できる部分は沢山ある」という言葉を聞いて、今後、教員になった時は、子どもたち一人一人への日々の声かけや、関わりを大切にしたいと思いました。
今回の講義より日本の教育と世界の教育は大きく異なり、良いところも悪いところもあるのが現状だと分かりました。また、小学校教員は子どもたちの人格形成に大きく影響与える立場であり、とても重い責任を担っていることがよく分かりました。私は子どもたち一人一人の個性も尊重することで、子どもたちも他者を尊重できるようになっていくのではないかと考えました。今後も世界と日本の教育の違いについて関心を持ち、まだ知らない文化から広い視点を得られるようになりたいと思います。